授業紹介
駒場アクティブラーニングスタジオでは、ディスカッション・グループワーク・デスクトップ実験・メディア制作などの能動的学習に対応するため、授業によって自由に構成を変えられるようになっています。また、専門スタッフがアクティブラーニングや協調学習型授業へのインテグレーションやコンサルティングまでお手伝いします。
駒場アクティブラーニングスタジオでは、能動的かつ高次な学習活動「アクティブラーニング」を導入した教養教育の授業を実践します。すなわち、学生が能動的に、現象・データ・情報・映像などの知識のインプットに対して、読解・作文・討論・問題解決などを通じて分析・統合・評価・意志決定を行い、その成果を組織化しアウトプットするような活動を取り入れた授業です。
本学で実績のある教養教育に、アクティブラーニングを取り入れ、さらにTablet PC等のICTを活用することで、より効果的に、より効率的に、学生が能動的に知識を組織化するような学習活動を促進しています。
2023年度(Aセメスターの授業一覧)・全13授業
| 曜日 | 時限 | 授業 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 2時限 | 英語二列W(ALESA) | TSAI Aurora Marjorie |
| 月曜日 | 4時限 | 後期課程/高度教養特殊演習(脳認知科学実習(1)「心理学実験」) | 中村 優子/ 浅水屋 剛/ 小池 進介 |
| 火曜日 | 2時限 | 全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習(模擬国連で学ぶ国際関係と合意形成I) | 中村 長史 |
| 火曜日 | 3時限 | ドイツ語一列② | 石原 あえか |
| 水曜日 | 1時限 | 英語二列W(ALESS) | ナオミ バーマン |
| 水曜日 | 2時限 | 全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習(模擬国連で学ぶ国際関係と合意形成II) | 中村 長史 |
| 水曜日 | 4時限 | 後期課程/高度教養特殊演習(広域英語圏地域論演習) | ロード・スミス |
| 水曜日 | 5時限 | 全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習(未来の学びを考える【理論と事例編】) | 中澤 明子 |
| 木曜日 | 4時限 | 地域文化論II | ロード・スミス |
| 木曜日 | 5時限 | 全学自由研究ゼミナール(平和のために東大生ができること) | 岡田 晃枝 |
| 金曜日 | 1時限 | 人文科学ゼミナール(データ分析) | 大森 拓哉 |
| 金曜日 | 2時限 | 全学自由研究ゼミナール/高度教養特殊演習(「オープン教材」をつくろう!) | 中澤 明子 |
| 金曜日 | 5時限 | 全学自由研究ゼミナール(駒場で「食」を考える) | 岡田 晃枝/ 渡邊 雄一郎 |
KALSでの授業事例
駒場アクティブラーニングスタジオでは、ディスカッション・グループワーク・デスクトップ実験・メディア制作などの能動的学習に対応するため、授業によって自由に構成を変えられるようになっています。また、専門スタッフがアクティブラーニングや協調学習型授業へのインテグレーションやコンサルティングまでお手伝いします。
ミクロの世界から探索的に学習する−生命科学


現代の生命科学では、様々な生命現象のメカニズムが分子レベルで解き明かされつつあります。KALSのAV設備を用いて、ビデオや画像などの豊富なビジュアルソースを見ながら、実際に目で見ることのできない生命現象のミクロの世界を、初学者でも分かりやすく学習できます。また、学習者はインタラクティブアニメーションや、最新データに基づいたコンピュータシミュレータによる3次元モデルを活用して、生命体の構造とその働きを、まるでミクロの世界から探索するように学習できます。
学生によって生命科学についての既有の知識や理解度が異なることもよくあります。
そこで教師は、KALSにセットされたパーソナルレスポンスシステムを使って、学生の理解度や反応をリアルタイムに把握しながら、より適切な解説を加えることができます。

渡邊雄一郎 教授
東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 生命環境科学系
大きな進展をとげつつある生命科学を実感しながら学習できる可能性を感じます。実体験できるマクロな生命と、現在の分子レベルで語られるミクロな生命科学とのあいだをつなぐ媒体としての期待をします。学生も受動的な学びから、能動的な学びへと意識改革できるのではないでしょうか。
映像アーカイブから生まれる新たな理解と知識構築−科学技術史


科学技術の急速な発展が社会生活に深く関わっている現代においては、科学技術史は教養教育にとって欠かすことのできない授業科目のひとつです。
具体的な「もの」と密接に結びついた科学技術史の学習には、文献資料のみならず、さまざまな媒体や情報に幅広くアクセスしていく必要があります。KALSでは、東京大学が開発した「MEET Video Explorer」を用いて、NHKアーカイブスの番組公開ライブラリに登録されている映像資料を検索・視聴することができます。これにより、課題に応じた効率的な学習や、ディスカッションのための素材の作成が可能になります。
さらに、グループごとのディスカッションでは、4面プロジェクタとマルチスクリーンを利用することで、相互の比較や多面的な討論を展開できます。

岡本拓司 准教授(2007年度当時)
東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 相関基礎科学系
科学史や技術史で取り上げる話題の中には、映像や現物として目に見える形で残されている事物を教材にできるものが多くあります。言葉による説明では理解の行き届かない場合も、映像があれば一目瞭然です。KALSとNHKアーカイブスを組みあわせて、学生自身が映像資料を探す実習を組むことで、成果にさらに期待が持てます。
タブレットPCを活用した思考訓練−English Academic Writing

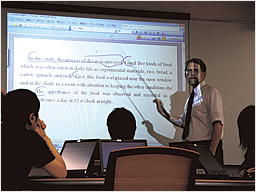
従来のライティング授業では、教師が学生に論文執筆のテクニックを解説するというスタイルが支配的でした。それに対して、タブレットPCを装備したKALSの学習環境は、学生が自分の思考を自分で論理的・批判的に文章化していくために格好のツールを提供しています。タブレットPCはネットワークを介して相互に接続されているため、教師は、一人ひとりの学生が書いている文章を個別にチェックできるだけではなく、それをスクリーンやインタラクティブボードに投影しながら、クラス全体にフィードバックしていくことも可能です。
また、アカデミックな方法論にもとづく文章表現を学習するために、グループに分かれて文献を調査し、相互に議論することで、論理的な思考過程そのものを着実に身につけることができます。

Tom Gally 准教授
東京大学大学院総合文化研究科 言語情報科学専攻(現職)
東京大学教養学部附属教養教育開発機構
クリティカル・ライティング・プログラム 特任准教授(2007年度当時)
新しい知は、三次元の空間で、多方向に行なう人と人の活発的なインタラクションからこそ創造されます。そのようなインタラクションを実現するアクティブラーニングのために設計されたKALSは、将来の教室、未来の大学の姿の先駆けであり、いつまでも知を創造しつづけるに違いありません。